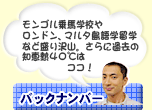夏休みの宿題にはあまりいい思い出がない。夏休みが終わる直前に取り掛かり、いい加減に仕上げ、それでも新学期に間に合わなくて「持ってくるのを忘れました」とみえみえのウソをついて毎年のように締め切りを引き伸ばしていた。
唯一、小学一年生のときの絵日記だけは、新学期になってから夏休みの優秀作品の一つとして校内に展示されたほど、しっかりしたものが提出できた。でもそれは祖父の助けがあったからだった。
その年の夏休みはほとんど祖父母の家で過ごした。一日の終わりに祖父の隣に座って絵日記を書くのが日課になっていた。祖父は小学校の元教師であり、絵や文章をいろいろと指導してくれたのだった。
中でも忘れられないのが、海に連れて行ってもらった日の日記だ。海を青い色鉛筆で塗りつぶそうとしたら怒られたのだ。
「海は青かったか?」
「うん」
「本当か」
「うん」
「よく思い出してみな」
「・・・・・・」
子供にとっては海は青しかなかった。私は答えに窮した。
「緑色のところがあっただろ」
そういわれてみればそうだった。あの海はエメラルドグリーンと青の部分がはっきり分かれていた。
自分の目で見たことをそのまま伝える、ジャーナリスト・相澤が誕生した瞬間だった。・・・・ウソ。まあそこまでじゃないけれど、結構その後の人生に影響のあった一言だと思う。
祖父と過ごした夏。プールでの出来事も忘れられない。祖父には、近所の町営プールによく連れて行ってもらったのだが、その日のプールには私と祖父以外誰もいなかった。祖父もただの付き添いで、水着などは最初から持っておらず、長ズボンとシャツを着たまま、プールサイドの日陰で寝転んでいた。
遊び相手もいなくて、泳ぐのに飽きてしまった私は、「今までに無い浮き輪の使い方」を考案し始めた。クリエイター・相澤が誕生した瞬間だった。・・・・これも大ウソ。「今までに無い浮き輪の使い方」というのは、すなわち「決してやってはいけない使い方」のことである。その浮き輪は二つの浮き輪が8の形にくっついたものだったので、前の浮き輪をリュックサックのように背負い、後ろの浮き輪に両足を通してプールに飛び込んだ結果、溺れたのだった。誕生どころかあやうく命を落とすところだった。手足の自由を奪われたうえ、顔を水から上げることもできない。ものすごく苦しかった。あの苦しさは今でもはっきりと思い出せる。ただその後の記憶は少し途切れる。気付いた時にはプールサイドに横たわっており、祖父が長ズボンを干していた。祖父が服を着たまま飛び込んで、助けてくれたのだ。祖父は私の命の恩人なのだ。記憶はないけれど、人工呼吸などもしてもらったかもしれない。そうすると、祖父は私のファーストキスの相手ということにもなるが、今となっては確かめることができない。
祖父はこの二ヶ月で急速に体調を悪くしていて、今やベッドに横たわり、酸素と水分の吸入を受けている状態で、意識はしっかりしているものの、肺に力がないため言葉がなかなか聞き取れないのだ。
もう老衰といっていい状態であり、祖父の部屋にはたくさんの子や孫が入れ替わり駆けつけ、見守っている。幸せな最後を迎えることができるといっていいと思うが、親戚たちに言わせると、初孫である私にいまだに嫁がいないことだけが唯一の心残りということになるそうだ。中には「誰か女の人に頼んでここまで来て貰って、結婚しますってウソついちゃえば」と超無責任な提案をする親戚もいた。
そんな話を聞いていたのかいないのか、祖父がベッドのすぐそばに座っていた私に向かって声をかけた。私には全く聞き取れなかったのだが、周りにいた親戚によると、私に嫁はまだか?と聞いているらしい。本当にそんなこと言ってるかなー?そういう先入観を持って聞いてたから、そう聞こえたんじゃないの?と思ったが、ベッドの反対側にいた叔父が祖父の耳元で大声で怒鳴った。
「まだいねーってよ!」
心底情けない気持ちになった。「もっと早くやっておけばよかった。あんなに時間はあったのに」という、手付かずの宿題がいっぱい残った夏休み最後の日のような気持ち。叔父が私の代わりにさっさと答えてしまったから、あの言い訳も使えない。「持ってくるの忘れましたー」