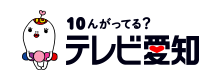日本語教師体験記
スマホの機種変更をした。
スマホショップの店員の敬語が丁寧すぎて、ちょっと面白いことになっていた。
「お客さまのスマホにおさわりいたしますね」
「いたします」を付けるから変なのか?
いや「おさわりします」でも変だ。
スマホに対して敬語を使っているような気がするし、なんだか猥褻な感じもする。
つくづく日本語は難しい。
今私はそんな日本語と格闘している。
日本語教師になるための学校に通っているのだ。
先日、初めて教育実習の教壇に立った。
まったくもってうまくいかなかった。
ボコボコにされた。いや、ボッコボッコにされた。
ポジティブな言い方をすれば『多くの学びがあった』ということになるかもしれないが・・・・。
生徒は中国人2人、韓国人、エジプト人、モンゴル人、合わせて5人。
本当の生徒ではなく、生徒役のアルバイトとして集められた人たちだ。
もう何度も生徒役を演じてきているプロフェッショナル生徒だ。
今回は「初級レベル」という設定になっている。
私がこの日教えることになっていたのは『伝聞のそうです』だった。
最初に「あすは晴れるそうです」といった文を教え、さらにその情報をどこで知ったのかを示す「~たんですが」を付けた文を教える。
「天気予報で見たんですが、あすは晴れるそうです」といった具合だ。
早速質問が出る。
「先生、『天気予報で見たんですが』よりも『天気予報によると』のほうが使うと思います」
「いえ、普段話すときは『見たんですが』のほうが多く使われます」
「そんなことないです」
なぜ、生徒であるあなたが断言するの?
「『によると』は、話すときよりも、論文などを書くときに使います。あらたまった場所で使います」
「『あらたまった』って何ですか?初めて聞きました」
・・・なぜ『によると』は知っていて、『あらたまった』は聞いたこともないのか?
「『あらたまった』というのは、ニュースとか、大勢の人の前で話すときとか、スーツを着ているような状況で話すときです」
「スーツを着て友達を話すときはどうしますか?」
「・・・その場合は『~たんですが』でいいですよ」
質問されているというより、因縁をつけられているような気もしてきたが、授業を進める。
左に新聞のイラスト、右に台風のイラストを並べたスライドを見せた。
新聞と台風の間に「~んですが」、台風の右には「そうです」と書いてある。
「新聞で読んだんですが、台風が来るそうです」という文を生徒に言わせようとしたのだ。
ところが、指名した生徒はこう答えたのだった。
「新聞で見たんですが・・・」
「あ、新聞の場合は『読んだんですが』のほうがいいですね」
「何でですか!『見た』でいいと思います」
「何でですか!」と言われましてもね・・・・・
『読みます』と『見ます』はどう違うのか?なぜ新聞は『読みます』のほうがいいのか?
この程度のことでも説明するのは難しい。
なにしろ生徒は『初級レベル』なので、簡単な日本語しか使ってはいけないという制限があるのだ。
「『読む』というのは、ただ『見る』のと違います。内容を理解・・・・わかるために時間をかけて・・・読みますよね。『見る』だと新聞の見出し・・・・大きい字のところを見るくらいで、詳しい内容はわからないですよね?・・・うん、『読む』のほうが『見る』よりも長い時間がかかりますね。『見る」だと時間が短いです。チラっと見ただけでは・・・」
その瞬間、生徒たちが叫んだ。
「チラっと!!!!」
外国人には日本語の擬態語・擬音語のニュアンスは伝わりにくい。日本語教師が擬音語・擬態語を使うのはタブーとされている。
それを知っているプロフェッショナル生徒たちが私のミスを指摘したのだ。
それにしてもあんなに一斉に「ダウト!」みたいな感じで言われて、へこんだ。
気を取り直して、次のスライドへ。今度はテレビのイラストだ。
「テレビは『見たんですが』を使います」
「先生、エジプトでは『テレビを聞く』と言います」